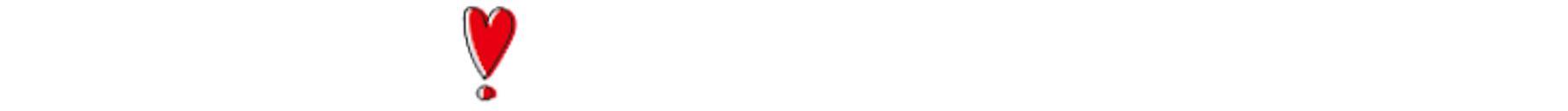叱っても勉強してくれない。よくある親の悩みです。勉強しないこどもには2通りあると思います。
・勉強をやったほうがいいと自分で思える子供
・勉強やれといわれても気にならない子供
前者の子供は環境を整えれば、勉強をやるようになってくれると思いますよ。
快楽を満たせる環境が、勉強を阻害する

子供も、義務と快楽のはざまで葛藤しています。
人は不快から快楽に移行したい生き物です。快楽を満たせる環境が身の回りにあると、それ以下である勉強は不快になります。だから勉強したくありません。
これを逆手にとると勉強します。
制限された環境で、行動の選択肢が絞られるからこそ、その中でできる行動を模索します。
傾向がわかれば対策がとれます。
✅家の中だと食卓がベスト
勉強してほしいなら快楽を削ること、選択肢がない環境がベストです。
わかりやすいのはカフェや、通勤電車です。自分の部屋じゃないからだらっと寝ころがってテレビはみれません。周りの目を気にするからです。子供部屋よりも圧倒的に食卓のほうが勉強する理由がこれです。
周りに興味のあるものがない環境だったら、人は無為に時間を費やすよりも何かを生み出そうとします。人は時間をつぶすよりも価値あるものに使うことが快楽だからです。
僕も凡人なのでアイデアを練るときは、何もない環境のほうが絶対に集中できます。
勉強するには学校が最強

人は、まさに環境です。
人からよく見られる、というのは快楽につながります。 逆に人から悪くみられたくないのは、快楽への動機づけにつなります。
子供が尊敬する先生が教えてくれるなら、好かれたいために自分の行動を先生の好みに合わせます。また怖い先生の場合、怒られないために勉強します。怒られないことが結果、快楽につながるからです。
快適さが制限される + 快楽につながる人間関係 = 学校
2重の意味で学校は、勉強に最強な場所です。
✅勉強への意欲がもてる環境をつくる
たとえば以下です。
1.塾に通わせる
2.家庭教師を雇う
3.親戚、友達と一緒に勉強させる
4.食卓で親が家庭教師になるずれしかありません。
友達と一緒だと勉強しやすいイメージありますよね。あいつもやるから俺もやるという状況です。 好きな異性が近くにいたらよく見せたいのでがんばってやろうとします。わかりやすいです。
親戚が勉強をみてくれるとかも、いつも通りの環境じゃあないですよね。子供が勉強やりそうな期待が持てます。
たとえば最近だとリモートワークしていて、家庭だと仕事に身が入らない。会社のほうが集中できるといのも同じ理由かもしれません。
僕も、よほど集中してないと、ついついほかのことが気になります。
人がいるほうが勉強がはかどる理由

実は、いままで語ったことには根拠があります。
集団で同じ課題に取り組むことで、より成果があがる。誰かが傍にいることで意識が冴えて集中力が増す、社会的促進(フロイド・ヘンリー・オルポート)という考え方です。
周りに人がいてくれたほうが、勉強する気になるの、よくわかります。
✅親がみてるだけでいい
実は子供をみているだけで効果があるそうです。教えなくてもいいんです。だから食卓で勉強させることが、子ども部屋で一人で勉強させるよりも効果的なんです。 何より勉強やる気になるのが大きなポイントですよね。
同様に誰かが一緒に勉強している、ということも勉強が進む効果がみられます。「私もお皿洗うから一緒にがんばろうね」みたいに家事しながらをやるとかありですよね。
僕も作業しながら、子どもがそばにいてよく遊んでいることはあります。「父ちゃんも仕事するから、君も ラキュー がんばってくれ」みたいな感じです。
しかし、一つだけポイントがあって、課題が難しい場合は、ひとりでさせないと結果が悪くなるという実験結果があります。うまくいかないときに人が周りにいると余計にイライラするみたいなものです。
実際、僕の子供もラキューで遊んでますが、難しいやつをつくっていると、「あー!!!!もー!!!!!」唸って地団駄踏みそうなテンションになります。校の宿題や課題程度なら食卓が一番だということでいいと思います。
勉強させなくてもいいという考え方
「勉強して!」とうるさくいわなくてもいいとしたら、親はきっと楽だとおもいます。
ただ、最高の環境である学校で勉強しないなら、どんなに親が努力しても無理だろうということもわかっていただけたと思います。
そんな子供に親ができるのは、子どもが生きていくうえで役に立ちそうな分野を探し支え、伸ばすことです。
これはとても勇気がいることかもしれません。
✅伸ばせるものを探す
音楽、ゲーム、プラモデル、サッカー・・・特別に好きな分野があるはずです。
それをどう社会活動に活かせるか、親はそれをつなぐだけです。
・コミュニケーション活動を研ぎ澄ませる
・手や足、肉体の技術的な使い道を先鋭化させる
・知識を習得していくことの楽しさを追求させる
こんなふうにいくらでも実際の職業に活かせることはあります。
親が子供の特性を見ながら、子どもの長所を伸ばす支援ができます。
「勉強しろ」と言って子供から逃げるのは、カンタンなんです。
すみません、いじわるな言い方で。
学歴が高くなくても社会でやっていけます
最高の環境である学校で学べないのなら、学校の勉強は難しいです。それでも人生なんとかなると思います。
現場で学びさえすれば、よほど専門的な仕事でない限り対応できます。一方で、採用されるためにも高学歴がいい、という意見にもうなづけます。学歴という通行手形がほしいだけなんですよね。
実社会にでてみれば、会社で管理職といわれる人で、言葉遣いを知らない、 漢字が読めない、なんて人は自分の知る範囲でもそこそこいます。また学歴がなくても、どこでもやっていける人間性を持つ人はいます。
僕も高校まで通いましたが、夢である声優になるために、毎日、発生練習や筋トレしつつ、学校の図書館に通って心理学、成功哲学の本を読んでました。
興味のない勉強よりも、よほど自分の将来にとって大切だと思ったからです。
後にコンサルの社会に入って、その知識と経験がものすごく活かされました。学生時代よりも社会人になってからのほうがよほど勉強しています。
親にできるのは子供が情熱をもって取り組むことへの支援だと思います。ただ、子どもを認めて理解してあげるだけでいい。
親は子供のそばで見ているだけでいいんだと思います。