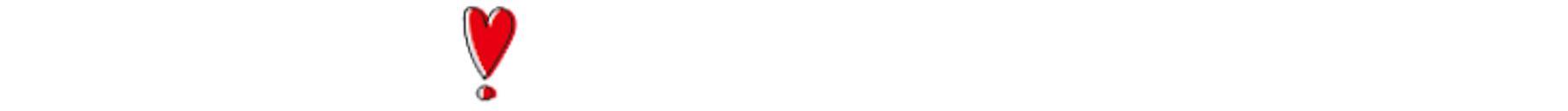日本人の10人のうち7人が
この不安気質といわれます。
ストレスに影響を与る要素です。
不安気質の子供は、
先見性があり、
計画性がある。
長期リスクマネジメントの
スペシャリストですヽ(=´▽`=)ノ
ただ、デメリットもあって、
何事にも神経質に反応、
否定的な妄想をしがち、
慎重すぎるという傾向もあります (ノ◇≦。)
そんな執着気質の強い子供の
親として気を付けたいポイントは、この3つ。
1.つねに不安
2.決断できない
3.激高する
1.つねに不安
非常に敏感なため、
ちょっとしたことで、不安になっています。
ただ本人はそう自覚していません。
それが当たり前だからです。
“びくびくすることが頻繁に起こる”
これが不安気質の日常です。
・いきなりドアが開く
・どこかで大きな声がする
・携帯電話がなる
これを怖いと感じています。
自分に何か悪いコトがおこる、
怒られるとか、
何かを失うとか (゚ω゚;)
そういう連想をしてしまいます。
不安じゃないタイプからみると、
到底理解できないです。
でも、それを
日常的に感じているのが
この不安気質です。
日本人なら多くの人が、
なんとなくわかるんじゃないでしょうか。

不安気質が強いと、
ちょっとした表現でも子供は不安を感じます。
親の声や表情に、少しでも険があると不安です。
冷たかったり、トゲがあったり、
ちょっと突き放したりすると、
それだけで不安なんです。
子供は、やばい(不安)と感じます |ョ゚Д゚。)
不安だから、親との関係を改善させなければ!
そうやって、
愛情を得るための努力を始めます。
そして穏やかな表情や声を得られると安心します。
不安がりなこどもは、
コントロールされやすいのです。
不安気質が低い親は、
子供がなんで怖いのか、
一生わかりません。
まず大切なのは、
不安を感じてしまう子供を
認めてあげることです。
そして・・・
「お父さん、お母さんは、
いつでもあなたのミカタだから」
これを、いつもことばで
伝えてあげてください。
そうすれば、その信頼関係は
ほかの気質をもつ子よりも
より深いものになります。 (..、)ヾ(^^ )
2.決断できない
不安だからカンタンに決断できません。
いろんなことが気になります。
過去のこと、将来のこと、
知り合いのこと、そして親のこと、
決断は誰にとっても簡単じゃありません。
不安気質の子は、
決断するための要素があまりにも膨大です。
ただ、これは非常にすばらしい特質です (*゚ー+゚) ☆
だからこそ、
不安気質の多い日本人は、
世界からみても、安心だと感じられる
社会を実現しています。
親としてできることは、
子供の話を聞いて、余計な不安は脇に置くように
交通整理をしてあげてください。

子供は、過度の心配で
悲観的になっています。
勝手な勘違いで、
妄想に迷い込みんでいます。
あれ、おかしいな?
と感じたら、声をかけて
心のねじれをほぐす手伝いを
してあげてください。 d(*⌒▽⌒*)b
信頼関係をつくることです。
何かあればすぐに愚痴れる関係を
親子でいつも確認です。
3.激高する
不安な状況になるのは誰だって嫌です。
この不安気質だと、怒られることは、
それが何倍にも感じられています。
すごい孤独であり恐れです。
だから恐怖に対して防衛します。
なぜ、そんなに自分を怖がらせるのか、
不安にさせるのか許せません ヾ(`Д´*)
怒りとしてそれが現れます。
怒りは自己防衛の叫びなんです。
気にならない親は、
なんでこんなに反応が激しいのか、
びっくりすることありませんか?
実は、声があげられるだけいいのです。
声があげられない恐怖ほど
怖いものはないのです (。>0<。)
親に怒り返してくるのなら、
ちゃんと言える関係です。
親として不安気質をもつ子には
できるだけ怒らないように。
そして叱り方を学ぶんでみては
いかがでしょう。
そしてまちがっても、
子供をおどすことのないように。
お気をつけください ヽ(´▽`)/
まとめ
1.つねに不安 → 認めてあげる
2.決断できない → 整理する手伝い
3.激高する → 怒る×脅す×
不安気質を持つ子には、こう接してみてください。
見えない怪物。
恐怖には打ち勝つ最高の方法は、
見えることです。
どんなに怖い映画でも、お化け屋敷でも同じです。
怖いのは怪物が見えないからです。

見えないから、
勝手な想像や妄想をして
パニックを起こします。
これは感染症も同じです。
明確にデータがないから、
勝手な憶測でパニックが起こります。
飛沫感染なのか、空気感染なのか、
何メートルまでなら安全なのか、
何日間隔離があれば感染はない。
これが明確であれば安心します。
はっきり見えないから不安になるんです。
みえると怖さはなくなります。
対処が明確になるから、
理解できれば、
マネジメントできるようになるからです。
具体的には、
メモをするように子供に伝えてください。
見えれば対策を立てるのが、
もっともうまいのがこのタイプです。